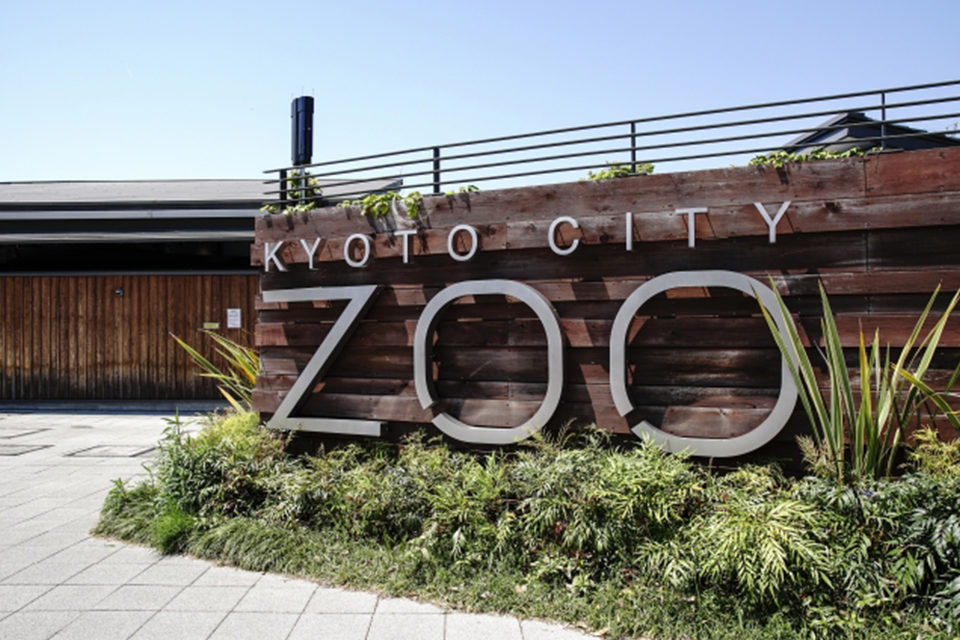平安遷都を実行したのは桓武天皇ですが、平安王朝の体制確立に大きく寄与したのは、第2皇子の嵯峨天皇だったとも言われます。北嵯峨の大覚寺は、かつては嵯峨天皇の別荘だった場所。門跡寺院として尊重された経緯より、現在の大覚寺で表の現れるのは江戸時代初頭の風合いですが、細部を掘り下げれば嵯峨天皇の時代まで一気にさかのぼることもできます。
嵯峨天皇の名跡として
 北嵯峨の大覚寺は、平安時代前期の嵯峨天皇が営んだ別荘(専門的な言い方では「別業」といいます)を、天皇の崩御後に皇女の正子内親王(淳和天皇皇后)が寺院に改めたもので、貞観18年(876年)を創建の年としています。現在の大覚寺は「旧嵯峨御所大覚寺門跡」を正式名称としており、その名が示す通り、歴代天皇や皇族が多く住持を務めてきた門跡寺院です。このように成り立ちの段階から皇室とは密接な繋がりがあり、伽藍の数々は御所をはじめ、皇室とゆかりのある建物が移築されたケースが多く見られます。中でも有名なのは宸殿および正寝殿です。
北嵯峨の大覚寺は、平安時代前期の嵯峨天皇が営んだ別荘(専門的な言い方では「別業」といいます)を、天皇の崩御後に皇女の正子内親王(淳和天皇皇后)が寺院に改めたもので、貞観18年(876年)を創建の年としています。現在の大覚寺は「旧嵯峨御所大覚寺門跡」を正式名称としており、その名が示す通り、歴代天皇や皇族が多く住持を務めてきた門跡寺院です。このように成り立ちの段階から皇室とは密接な繋がりがあり、伽藍の数々は御所をはじめ、皇室とゆかりのある建物が移築されたケースが多く見られます。中でも有名なのは宸殿および正寝殿です。宸殿と正寝殿
大沢池
 他にも東側の大沢池に張りだした濡れ縁(観月台)をもつ五大堂や大正天皇即位式の饗宴殿を移築した心経殿など、特徴のある建造物が並びます。こうした殿舎等の建造物やそれぞれの内部を飾る障壁画は、大覚寺拝観の大きな魅力ですが、より幅広くの人気を集めているのは、大沢池散策ではないでしょうか。大沢池は、大覚寺境内の東側にある周囲約1kmにおよぶ人工苑池で、梅林や竹林のある北辺の庭園エリアでは季節ごとの見映えを楽しむことができます。紅葉シーズンも例外ではなく、赤く染まった木々の彩りは、池の美しさを存分に引き立ててくれます。
他にも東側の大沢池に張りだした濡れ縁(観月台)をもつ五大堂や大正天皇即位式の饗宴殿を移築した心経殿など、特徴のある建造物が並びます。こうした殿舎等の建造物やそれぞれの内部を飾る障壁画は、大覚寺拝観の大きな魅力ですが、より幅広くの人気を集めているのは、大沢池散策ではないでしょうか。大沢池は、大覚寺境内の東側にある周囲約1kmにおよぶ人工苑池で、梅林や竹林のある北辺の庭園エリアでは季節ごとの見映えを楽しむことができます。紅葉シーズンも例外ではなく、赤く染まった木々の彩りは、池の美しさを存分に引き立ててくれます。![caedeKyoto[カエデ京都] 紅葉と伝統美を引き継ぐバッグ](https://caede-kyoto.com/wp/wp-content/uploads/2024/07/メインロゴ.png)