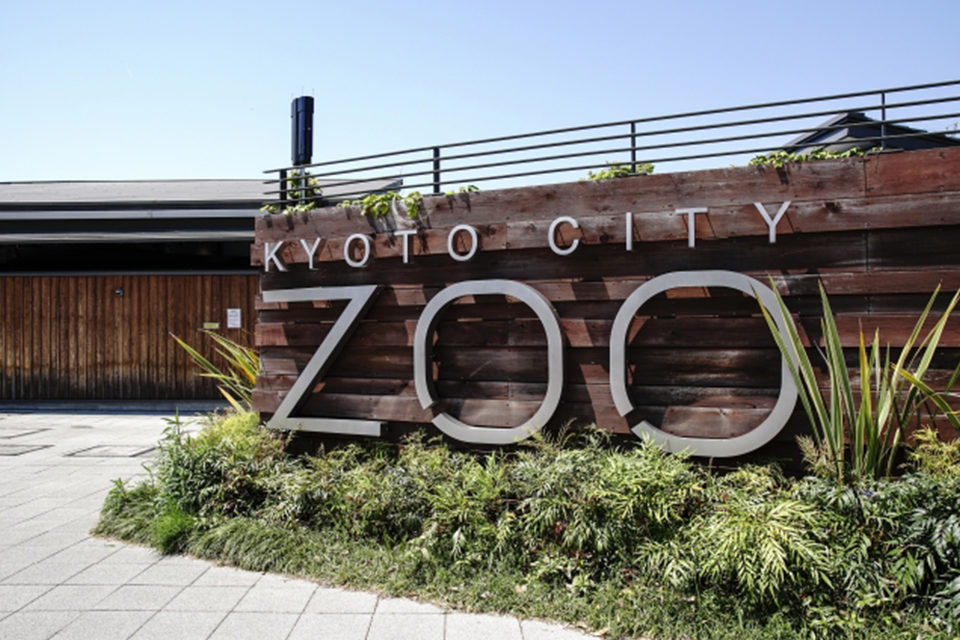岡崎の地に約6600㎡、甲子園のおよそ3倍の面積を占めるのが平安神宮です。歴史的には決して古いとは言えませんが、小川治兵衛が心血を注いで作り上げた池水回遊式庭園(平安神宮神苑)があって、観光客の幅広い支持を得ています。紅葉など木々の彩りだけでなく、平安時代を見つめ直す意味でも訪れるの価値のある場所です。
上賀茂神社や下鴨神社など、あるいは松尾大社や八坂神社など、京都で観光スポットとなっている神社は、長い歴史を誇っているところがほとんどです。それらに比べると平安神宮は、明治28年(1895)に左京区の岡崎に建てられたかなり新しい神社です。明治時代だからかなり古いと言ってはいけません。他の有名な神社は、平安時代以来、あるいはもっと長い歴史のところばかりなのですから。第4回内国勧業博覧会と平安神宮
京都市民の神社として
 そうした方向性があったため、京都の政財界は総力を挙げてこのイベントに取り組むこととなります。市民全体で盛り上げようという動きとなり、神社一般でいうところの氏子組織に相当する平安講社という団体が市内各地域に作られました(ちなみに府民ではなくて市民となっているのは、新しく策定された市制に基づいて明治22年に京都市が成立したため)。平安神宮創建に合わせて組織されたこの平安講社が、現代でも神宮祭礼でもある時代祭の担い手となっています。ところで平安遷都と言うと、よく知られているのように、鳴くよ鶯の794年なのですが、翌795年に桓武天皇による最初の元日朝賀(朝廷行事の中で最も重要とされる儀式)が平安宮大極殿で催行されたことを記念するという意味づけで1895年が遷都1100年となったのでした。こうした背景より、京都に暮らす人々が1000年の都だった平安京を誇りに思えるようにすることが創建の理念となったのでした。祭神に桓武天皇が選ばれたのも、平安京の生みの親たる天皇を崇めるという意味で必然であり、平安神宮を構成する社殿が平安宮の再現(サイズを5/8に縮小して大極殿や応天門が復元)したものになったのも、また必然的なものでした。
そうした方向性があったため、京都の政財界は総力を挙げてこのイベントに取り組むこととなります。市民全体で盛り上げようという動きとなり、神社一般でいうところの氏子組織に相当する平安講社という団体が市内各地域に作られました(ちなみに府民ではなくて市民となっているのは、新しく策定された市制に基づいて明治22年に京都市が成立したため)。平安神宮創建に合わせて組織されたこの平安講社が、現代でも神宮祭礼でもある時代祭の担い手となっています。ところで平安遷都と言うと、よく知られているのように、鳴くよ鶯の794年なのですが、翌795年に桓武天皇による最初の元日朝賀(朝廷行事の中で最も重要とされる儀式)が平安宮大極殿で催行されたことを記念するという意味づけで1895年が遷都1100年となったのでした。こうした背景より、京都に暮らす人々が1000年の都だった平安京を誇りに思えるようにすることが創建の理念となったのでした。祭神に桓武天皇が選ばれたのも、平安京の生みの親たる天皇を崇めるという意味で必然であり、平安神宮を構成する社殿が平安宮の再現(サイズを5/8に縮小して大極殿や応天門が復元)したものになったのも、また必然的なものでした。![caedeKyoto[カエデ京都] 紅葉と伝統美を引き継ぐバッグ](https://caede-kyoto.com/wp/wp-content/uploads/2024/07/メインロゴ.png)